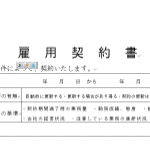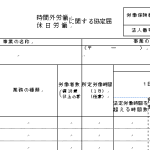労働時間になるもの
労働時間に算入されるものは、裁判所の判例の積み重ねによって明示されています。判例では労働時間は「労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。」とされています。
すなわち、労働契約や就業規則に労働時間は9:00~18:00と定められていても、使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうかという事が問題になってきます。
以下では、実際に労働時間に該当する作業について説明します。
始業前の準備、終業後の片付け
本来の業務の準備作業や後片付けについて、事業所内で行うことが使用者によって義務づけられている場合や現実に不可欠である場合には、原則として使用者の指揮命令下に置かれたものとされ、労働基準法上の労働時間に該当すると判断しています。
原材料や製品の整理整頓、機械の点検調整等、本来の作業に必要な準備作業、作業終了後の後始末、商店等における開店準備、閉店後の片付け等に要する時間は、特に使用者の指示命令がなくても本来の義務に付随して発生するものですから、労働時間に算入されるべきです。
これらの時間が労働時間に含まれるかどうかの判断は、
(1) 使用者の命令があるかどうか
(2) 当該作業を行うために必然的なもの、あるいは通常必要とされるものであるかどうか
(3) 法令で義務づけられているかどうか
などの点から検討される必要があります。
着替え
作業開始前の着替えの時間について、使用者から事業所内において行うことを義務づけられている場合などは、使用者の指揮命令下に置かれたものとされ、社会通念上必要と認められるものについては労働時間に該当すると判断しています。
使用者から義務付けられた作業服や保護具の着脱等に要した時間について、労働者が就業を命じられた業務の準備行為と認めて、これを労働基準法上の労働時間としています(三菱重工長崎造船所事件 最高裁 平12.3.9)。
一般的な更衣時間は、任意のものであれば労働時間とする必要はありませんが、あらかじめ義務付けられている制服の着脱時間や安全具の装着時間は逐一指揮命令されていなくても、一定の強制力がある場合には労働時間に含まれると解されます。
法令に義務付けられていない制服などの更衣時間については、労働時間に含めるか否かは、「就業規則に定めがあればその定めに従い、その定めがない場合には職場慣行によって決めるのが妥当(日野自動車工業事件 最高裁第一小法廷判決 昭59.10.18)とされています。
就業規則に、『始業時刻の前に着替え等を済ませておいて、始業時刻に勤務ができるように準備をしておくこと』まで規定した場合は、着替えの時間も労働時間とみなされます。制服の更衣などの時間については、どのように取り扱うのか、就業規則等で規定しておくのも労働紛争防止策の一つです。
手待ち時間
手待ち時間とは、使用者からの命令があればただちに業務に就くことができる態勢で待機している時間のことをいい、具体的には以下のような時間のことを指します。
労働基準法では、一定の時間を超えて働く労働者に対して、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならないことが定められています。手待ち時間については、それが休憩時間なのか労働時間なのかという点が問題となります。
1.店員が顧客を待っている時間
過去の判例では、勤務時間中の客の途切れた時などを見計って適宜休憩してよいとされている時間について、いわゆる手待ち時間であって休憩時間ではなく、労働時間に当たると判断しています。
2.夜間の仮眠時間
こちらも過去の判例で、「24時間勤務の途中に与えられる連続8時間の「仮眠時間」は、労働からの解放が保障された休憩時間とはいえず、実作業のない時間も含め、全体として使用者の指揮命令下にあるというべきであり、労働基準法上の労働時間に当たる」として、仮眠時間が労働時間であると認められています。
仮眠時間はいわゆる不活動時間ですが、労働から離れることが保障されていないと判断される場合、つまり何かあった場合にただちに相当の対応をしなければならないような状況下にあるときは、労働時間に該当します。
ビル管理会社の従業員が管理・警備業務の途中に与えられる夜間の仮眠時間も、仮眠場所が制約されることや、仮眠中も突発事態への対応を義務づけられていることを理由に、労働時間に当たるとする判例があります(大星ビル管理事件 最高裁 平14.2.28)
3.電話番の時間
昼休み中に電話番や来客対応をさせることについて、厚生労働省は「明らかに業務とみなされる」として、労働時間に含まれると示しています。
「昼休み当番」として、従業員が交替で昼休みの電話番と来客応対をしていて、この「昼休み当番」の時は自席で昼食をとっているという場合、昼休み時間中事務所内にいることが義務づけられており、電話や来客があった場合にはこれらに対応しなければならないため、「手待時間」として労働時間となります。この場合は休憩時間を他に与えなければなりません。なお、その際は、法第34条第2項ただし書による労使協定を締結しなければなりません。(昭和23年4月7日 基収1196号、昭和63年3月14日 基発150号、平成11年3月31日 基発168号)
4.物品の運搬・運送
出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等について特別の指示がなされている場合は、使用者の指揮監督下にあるといえますので、労働時間に含むものと考えられます。
貨物取扱の事業場で貨物の積み込み係が貨物自動車の到着を待機して身体を休めている場合は、手待時間ですから労働時間に含むものと考えられます。
運転手が2名乗り込んで交互に運転にあたる場合に、運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠している場合は手待時間ですから、労働時間に含むものと考えられます。労働時間が8時間を越えれば、割増の残業代も支払わなければなりません。
時間外労働の黙認
従業員の自己判断で残業をしても、事後承認が慣行となっている場合は、格別の理由がない限り時間外労働として扱わなければなりません。
勉強会・研修
勉強会や研修に参加している時間についても、労働時間として認められる場合があります。過去の判例では、労働者が月に1~2回程度、少なくとも20分以上を費やして開催される研修会に参加していた時間を時間外労働時間であると認め、会社に対して割増賃金を支払う義務があると判断しています。
勉強会や研修については、参加が義務づけられている・欠席による罰則などがある・出席しなければ業務に最低限度必要な知識が習得できない、といった場合には、労働時間として認められる可能性があるといえます。
参加が義務づけられている研修等は労働時間となります。
例えば、業務命令で休日に行われる合宿研修は、勤務扱いをしなければなりません。休日に労働させていることになるからです。研修終了後に振替休日を与えるか、休日労働として35%増しの割増賃金の支払いが必要となります。
安全衛生教育の時間
法に基づく安全衛生教育については、労働時間内に行うのを原則とします。労働時間と解されますので、法定労働時間外に行われた場合には時間外労働になり、割増賃金を支給しなければなりません。
健康診断
健康診断に関しては、厚生労働省が公式の見解を示しています。これによると、職種に関係なく定期的に行う「一般健康診断」は、業務遂行との直接の関連において行われるものではないことから、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきとしつつ、受診に要した時間の賃金を支払うことが望ましいとされています。
なお、法定の有害業務に従事する労働者が受ける「特殊健康診断」は、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断であることから、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間に該当し、賃金の支払いが必要であるとされています。
始業前の朝礼
使用者の指揮命令によるか否かで判断されることになります。
朝礼で点呼をとったり、当日の仕事の流れを説明するような場合は強制参加であるため、労働時間となります。
強制ではないが、朝礼への参加状況が人事考課に関係する場合も労働時間と判断されます。
帰宅後の呼び出し
労働に中断があっても、1日につき8時間を超える場合は時間外労働になります。
そのための往復の通勤の時間は、労働基準法上は通常の通勤時間と同一のものとして労働時間には該当しないものと解されます。往復の通勤の時間賃金の支払いは不要です。
有給休暇中に緊急の呼び出しで出勤したという場合、原則、有給は取得しなかったものとして扱われ、通常の出勤日となります。賃金も労働時間に対して支払うことになります。
労働時間とみなされない時間
以下のような作業に要する時間については、労働時間とみなされないため注意が必要です。
通勤
通勤自体は働くために必要な作業となりますが、通勤時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としては判断されません。
タイムカードの打刻
事業場に入ってから、タイムカード等の置いてある所まで行くのに要する時間は、労働時間には入りません。(三晃印刷事件 東京地裁 平成9.03.13)
法令に義務付けられていない制服などの更衣時間
法令に義務付けられていない制服などの更衣時間については、労働時間に含めるか否かは、「就業規則に定めがあればその定めに従い、その定めがない場合には職場慣行によって決めるのが妥当」(日野自動車工業事件 最高裁 昭59.10.18)とされています。作業するために不可欠なものであっても、働くための準備行為なので労働力そのものではないので、更衣時間については原則として労働時間に含めません。
朝の掃除、準備
従業員が自主的に掃除などをしている場合は、本人の自発的な行動とみなされ、労働時間にはなりません。
始業前の掃除やお湯を沸かしたりすることを命じられていたり、当番制によって事実上強制になっている場合で、黙示の業務命令があるとみなされた場合は労働時間となります。
始業10分前の出勤を指示された場合
「使用者の指揮命令下にあって労働力を提供している時間」にあたるかどうかにかかってきます。「実際に働いているかどうか」ということで、拘束力が弱く業務を行っていない場合は、指揮命令下にあって労働力を提供しているとは言えず、早出とみなされる可能性は低いと思われます。
朝礼、ミーティング等で、参加が義務づけられている場合には労働時間となり、早出として時間外手当を支払う必要があります。
始業前のラジオ体操
「参加は従業員に強く奨励されていたが、義務付けられていたということはできない」として、労働時間として認めなかった判例があります(住友電気工業事件 大阪地裁 昭58.8.25)。
休憩時間・始業・終業時刻の前後の自由時間
使用者の拘束下にありますが、労務提供のための指揮命令は受けておらず、労働から解放されているため、労働時間になりません。
自発的な残業
原則として、自発的に行なう残業については、労働時間として取り扱う必要はありません。残業は、使用者の業務命令があって初めて生ずるものだからです。
明確な業務命令がなかったとしても、残業を行なう労働者を黙認していた場合などは、黙示の指示があったものとして労働時間となります。
持ち帰り残業
持ち帰り残業とは、書類を自宅に持ち帰ったり、メールでデータを自宅のパソコンに送信しておいて、自宅で仕事(残業)を行なうことですが、自発的に行なう場合は原則として労働時間にはなりません。
作業後の入浴
労働安全衛生規則では、「事業者は身体または被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身もしくはうがいの設備、更衣設備または洗濯のための設備を設けなければならない」ことを定めています。ただし、入浴時間などについての規定はなく、入浴時間については使用者の指揮命令下にあるとはいえないと解されています。
厚生労働省の通知では、坑内労働者の入浴時間について、通常労働時間に算入されないと示されています。
一般健康診断の受診時間
従業員一般に対して行われる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないため、受診のために要した時間は労働時間として扱わなくても差し支えありません。
特定の有害な業務に従事する労働者について行われる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで実施されなければならない性格のものです。実施に要する時間は労働時間と解されます。
就業時間外の教育訓練
使用者が実施する教育に参加することについて、出席の強制がなく、自由参加のものであれば時間外労働にはなりません。このあたりのことを、就業規則には明確に定めておくとよいでしょう。
昇進・昇格試験を休日に実施した場合は、休日出勤にはなりません。報酬などの向上を目指すための昇格試験なので、労働時間とはみなされないのです。
受験しなかったときに給料の減額などの受講者にとって不利益な措置があるときは、労働時間とみなされます。
休日の接待ゴルフ
原則として休日労働とはなりません。
本人はプレーせず、コンペの準備や進行、送迎等の接待の任務をもって参加する担当者の場合は、それが使用者の命令によるものであり、かつ主たる業務として行なわれる限り労働時間となります。なお、開催が平日であれば、通常の労働時間として扱ってよいでしょう。
出張の移動時間
出張先への移動時間については通勤時間と同様に、その間は、会社の指揮・監督下にあるわけではなく、労働時間では無いとする見方が有力です。裁判例には、「出張の際の往復に要する時間は労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがって時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(横浜地裁判決昭和49年1月26日)。つまり、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解されます。
ただし、一度会社に立寄ってから向かう場合や、出張先から会社へ戻る場合にあっては、その時間は労働時間にあたると一般的には解されています。たとえば、営業で取引先をまわる場合などが想定されるでしょう。
また、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等について特別の指示がなされている場合には、使用者の指揮監督下にあるといえますので、労働時間に含まれると考えます。上司が同行しての出張の場合にも、会社の指揮・監督下にあるとして、労働時間にあたると解されています。
なお、労働基準法38条の2で「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」と規定されており、通勤途上による寄り道で、その時間の把握が困難な場合には、原則として所定労働時間(みなし時間)とし、時間外労働として扱わなくてもよいとされます。たとえば、弁護士の業務を例にとれば、朝裁判所に寄ってから事務所に行くという場合には、仮に就業開始時刻より早く裁判所に寄ったとしても、時間外労働と扱われないことになります。
出張中の休日に移動のため旅行する場合は、特段の指示がない限り労働時間に含める必要がないとされます(昭和23年3月17日 基発461 昭和33年2月13日 基発90号)。しかし、何らかの手当を支給するなどの方法で報いるのが良いと考えます。
。
自宅待機をさせた場合
場所的には自宅に拘束されるものの、その時間は自由に利用できます。事業場で使用者の指揮監督のもとに拘束される手待ち時間とは異なるものと考えられます。自宅待機の時間を「労働時間」とみなす必要はありません。
自宅待機について、賃金を支払いの定めはありません。しかし、休日に待機命令を行うことは、強制力をもって行うことには問題があり、労働時間とはならず、その手当も宿日直手当程度(平均賃金の3分の1)が相当と思われます。
休日に業務遂行を前提として会社に「待機」させる場合は、待機時間は労働時間となりますが、非常のときに備えて待機するだけのときは「日直」と扱うこともできます。宿日直手当程度(平均賃金の3分の1)が相当でしょう。