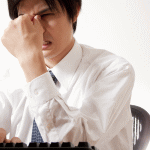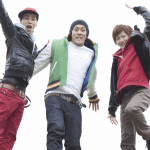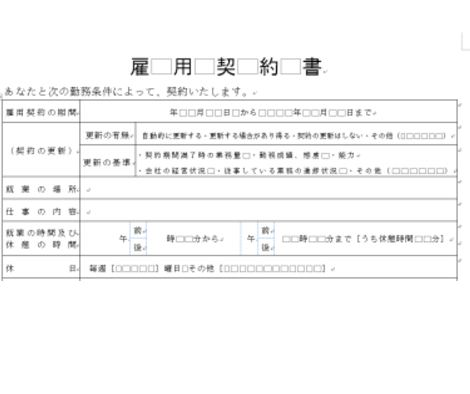時間外労働の上限規制のポイント(2019年4月から)
働き方改革による労働基準法改正で、労働時間に関する規制が強化されます。主なものは次のようなものです。
1.残業時間の上限規制により、月45時間、年360時間までの残業が基本となる。(現状と同じ)
2.特別条項つき36協定を用いることで、1年で6回までなら、1ヶ月の残業時間を100時間まで。1年の残業時間上限も720時間まで。(厳しくなります)
3.2019年4月から(上記1.2の)残業時間の上限規制が適用される。ただし中小企業は1年後の2020年からです。
4.タクシー、トラック運転手や医師など一部の業種に残業時間の上限規制は2024年から適用されます。
時間外労働の上限規制とは
今まで時間外労働の上限規制はどうなっていたのでしょう?本来、法定労働時間(週40時間1日8時間)を超えた労働は違法ですが、36(さぶろく)協定を締結すれば残業(時間外労働)をさせても良いということになっています。但し、36協定を届け出たからといって、無制限に残業をさせても良いというわけではありません。しかし、一時的に残業が増えることはどこの会社にもあり得ます。そのような時は36協定の特別条項を利用し残業時間を一時的に増やすことができました。
特別条項付きの36協定を締結することで、1年のうち6ヶ月に限り残業時間の上限規制が撤廃されます。1ヶ月×6回の合計6ヶ月間のみ、36協定で定められている時間を超えて無制限に残業させることができました。
この状況を改善するために働き方改革により、36協定による残業時間の上限規制をより強固にすることになりました。
働き方改革関連法施行前の限度基準告示による上限は罰則はあるものの強制力はなく、特別条項を設けることで実質は上限なく従業員に時間外労働を行わせることが可能でしたが、今回の改正によって労働時間の上限が法律によって定められ、臨時的な特別な事情がある場合でも上限を上回ってはならないとされています。守れなかった場合は罰則もあります。
年間での時間外労働の上限規制について
働き方改革による労働基準法の改正により、残業時間の上限規制が厳しくなり、特別条項付き36協定を締結しても、残業時間に制限が設けられるようになりました。
今までは年6回限定で、1ヶ月間の残業時間を無制限にできましたが、法改正後は1ヶ月の残業時間の上限が100時間に定められました。特別条項を利用しても、月100時間以上残業させたら違法になるのです。
2019年4月以降の残業時間の上限
1.平時の残業時間上限は、1ヶ月で45時間、1年で360時間。(今までと同じ)
2.特別条項を利用した場合、1年で合計6ヶ月の間だけ、月の残業時間上限が100時間まで延長できる。(但し、休日労働の時間も残業時間に含める)
3.特別条項を利用した場合、1年720時間以内の残業が認められる。
4.特別条項があっても、残業時間には複数月平均80時間以内の制限が設けられる。(休日労働の時間も残業時間に含める)
前述の通り、今までは36協定の特別条項を締結することで、時間外労働の上限規制を超えて労働させることができました。しかもこの特別条項には時間外労働の上限に関して明確な法律の定めがなく、長時間労働を指摘されても「年720時間以内が望ましい」という行政指導を受けることがある程度のものでした。
改正後も、基本的に時間外労働は月45時間・年360時間に収めなければならないことは変わりません。また、特別条項を締結しての時間外労働は認められますが、年間720時間以内・月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働も含む)・時間外労働45時間超えは年6カ月以内という条件をすべて満たさなくてはならなくなりました。これに違反した場合は、法律により罰金30万円or6カ月以下の懲役の罰則が科される可能性あるので注意が必要です。
複数月平均とは新しい概念なので解説します。
時間外労働時間は「複数月平均80時間以内」に
「複数月平均80時間以内」とは
例えば12月時点でこの基準に合致しているかを確認する場合、7~12月(6カ月平均)・8~12月(5カ月平均)・9~12月(4カ月平均)・10~12月(3カ月平均)・11~12月(2カ月平均)のいずれの場合でも平均の時間外労働が80時間を下回っている必要があります。
1つでも時間外労働時間が平均80時間を超えていると、12月の時間外労働は違法なものとなるため残業時間の管理が重要になります。
中小企業は2020年4月から適用されます
大企業では2019年4月1日から残業時間の上限規制が適用されますが、中小企業の場合は1年遅れて2020年4月1日からとなります。
規制を除外・猶予される事業や業務
中小企業への上限規制適用に猶予があるのとは別に、残業時間の上限規制に対する除外や猶予の措置がとられている事業が存在します。残業規制が遅れて適用される、または規制そのものが適用されないのは、以下の事業です。
土木、建設などの建設業・・・2024年4月1日
病院で働く医師・・・2024年4月1日
自動車を運転する業務(タクシー運転手など)・・・2024年4月1日
新技術や新商品などの研究開発業務・・・上限規制は適用されない
こちらに詳しく載ってます↓
働き方改革総合リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
その他の改正点
中小企業も時間外労働の割増賃金が50%へ引き上げられる(2023年4月より)
時間外労働が発生すると労働基準法の定めにより、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金は2008年の労働基準法改正により、大企業では月60時間を超える場合の時間外労働の割増賃金が50%に引き上げられました。中小企業には猶予されていましたが、働き方関連法の改正により2023年4月より割増賃金の引き上げが中小企業にも適用されることになります。
罰則について
2019年4月以降、上限規制を超えた違法な時間外労働に対して罰則が科されるようになります。さらに、臨時的な特別な事情がある場合であっても上回ることのできない上限が設けられました。これにより、時間外労働の上限規制に違反した場合、半年以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることになります。
違法労働となる例
36協定を締結していない場合、そもそも法定労働時間を超えての労働が違法になります。そのため、1日8時間もしくは週40時間を超えての労働自体が違法になります。
36協定を締結・特別条項を締結していない場合は、週15時間、1カ月45時間を超過しての時間外労働が違法になります。
36協定・特別条項のどちらも締結している場合は、下記のいずれかに該当する場合が違法になります。
年6回を超えて月45時間以上を超える時間外労働をさせること
月100時間以上の時間外労働をさせること
複数月の平均時間外労働時間が80時間を超えること
年720時間を超えて時間外労働をさせること